ぼくのニワトリは空を飛ぶー菅野芳秀のブログ
|
歯を見失った。入れ歯のことだ。下の歯の真ん中から少し左に三本、10年ほど前から部分入れ歯にしていた。そこはモノを噛むとき一番活躍するところで、無くなれば大いに不便で、まるで年朗さんみたいだ。年朗さんとは近くに住んでいる先輩で、半分ぐらい歯がない。モノを食べてもほとんど噛めずに、舌で丸めて飲んでしまう人だ。時々大きく口を開けて「フェッ、フェッ」と笑う。年齢よりも10歳は老け見えた。
「早く歯を入れないと身体を壊すよ」と忠告したが、笑うだけで歯を入れようとはしなかった。やがて年朗さんは身体を壊して入院してしまった。だから言わんこっちゃないと思っていたけど、今の俺はその年朗さん状態だ。たぶん見た目も悪かろうとわざわざ大口を開けて笑ったところを家族に見てもらったが、この点はまだ大丈夫だという。歯がない事までは分からないらしい。あとはかみ合わせだけだ。見失ってからもう5カ月。早く見つけなくちゃ。家の中にあることはほぼ間違いあるまい。 「えー、またか〜!」家族のこんな声を何回聞いただろう。家族だけでなく、歯医者さんまでもがうんざりした顔で俺を見る。当然だろうな。入れ歯を使いだしてから10年、今回で歯を失くしたのは9回目になるのだから。 初めて歯を作った時は「菅野さんは外で話すことが多いから、滑らかに話すためにもいい歯をお勧めるよ」とまぁ、こんなことだった。そこで勧められるまま大枚をたたいて30万円。でもその寿命はわずか半年だった。ピッタリと歯が入るのだが、つけ慣れないせいで少し圧迫感があるのが気になって歯を時々口から外してしまう。それが失くしてしまう全ての原因だ。 1回目は外した歯をチリ紙に包んで居間の机の上に置いていた。それを使用後のチリ紙と間違えられ、ゴミ箱へ。ゴミ箱からゴミ配送車へと30万円が消えて行った。次に作ってもらったのは家族の手前もあって、もう少し安いのにしたが、それも1年と持たなかった。次が・・・なくなるたびに入れ歯のグレードが下がって行く。最後の8番目の歯は国民健康保険で入れた9千円のもの。たぶん30万円から、国保で治した9千円まで段階を踏んでほぼ全てを試したのは日本広しといえども俺ぐらいだろうか。そこでの発見だけど、使った感じは30万円も9千円もほとんど変わらなかったよ。これって後に続く者にとってはとても心強く、かつ貴重な体験なのではないか。 えっ、今かい?歯はまだ入れてない。見失ったままだ。歯医者さんに「9回目ですが・・作ってください」 とはいえずに家族のヒンシュクを買いながら家の中を探し回っているよ。 |
12月9日は昔から「耳あけ」と呼ばれている日だ。
大黒様を祭ってある神棚に尾頭付きの魚と二つに分かれた「まった大根」をあげ、枡に大豆を入れ、カラカラ言わせながら 「お大黒様、お大黒様。耳をよ〜く開けて聞いておりますから、なにがええごどおしぇでおごやえ〜!(良いこと教えてください)」と大声で言う。 この行事が終わると、急速に暮れに向かい忙しさが増していく。もう一つの写真は、畑でとれた面白い形の大根。きざんで食べてしまうのは惜しい気がする。 かと言って他に使い道はないけれど・・。 
|
菅野農園のニワトリたちは「庭鳥」として、ゲージではなく大地の上で暮らしています。週に2〜3回は外に出ます。草を啄んだり、土を突っついたりと気ままに過ごしています。
安いからと言ってエサに植物とウイルスとを人工的に合体させた遺伝子組み換え作物は使用していません。すべて自然のものを与えています。黄身の色も自然の色。どのような意味でも薬の類は使っていません。 以前から食品としての卵に懐疑的だった芳秀が、自分の子どもに食べさせたい玉子はこれだ、というのが菅野養鶏のはじまりです。自然卵です。 できる方は、ご自分で飼ってみることを勧めます。家族一人あたり一羽でいいでしょう。余ったらお付き合いに活用できます。 な〜に簡単ですよ。まず農文協の「自然卵養鶏法」(中島正著)をお読みください。次に創森社の「土と玉子といのちと」(菅野芳秀著)を。ここも肝心ですぞ。 生ごみや周囲の草など、さらには蕎麦屋のかつおだし、パン屋のミミなどいろんなものがニワトリたちの餌になります。 鶏舎は日曜大工で十分。一日で建ってしまいます。広さは十羽で一坪ぐらいかな。おいしい玉子ができること請け合いです。 なによりも暮らしが楽しくなりますよ。 分からないことはわが農園にお尋ねください。 誰だって写真のようなニワトリの卵は食べたくないよな。 |
菅野農園のニワトリたちは「庭鳥」として、ゲージではなく大地の上で暮らしています。週に2〜3回は外に出ます。草を食んだり、土を突っついたりと気ままに過ごしています。
できる方は、自分で飼ってみることを勧めます。家族一人あたり一羽でいいでしょう。余ったらお付き合いに活用できます。 な〜に簡単ですよ。まず農文協の「自然卵養鶏法」(中島正著)をお読みください。次に創森社の「土と玉子といのちと」(菅野芳秀著)を。ここも肝心ですぞ。 生ごみや周囲の草など、さらには蕎麦屋のかつおだし、パン屋のミミなどいろんなものがニワトリたちの餌になります。 鶏舎は日曜大工で十分。一日で建ってしまいます。広さは十羽で一坪ぐらいかな。おいしい玉子ができること請け合いです。 なによりも暮らしが楽しくなりますよ。 分からないことは菅野農園にお尋ねください。く |
95歳の母親はショッパイモノが大好きだ。お茶のお伴は漬物だし、ご飯のおかずにはショッパイモノが欠かせない。妻が身体を考えて薄味の味噌汁を出すのだが「うすい」といって醤油をかける。「あっ、身体に・・・!」と止めようとするが、このような食生活を長年送ってきて結論が元気なのだから・・何も言うことはない。92歳の父親も同じようなもの。夫婦そろって元気なのは・・・良く働いた、なんでも食べる、酒は少しだけ、いつまでもクヨクヨしない・・などの原因も考えられるが、つまるところは自分流だ。自分流・・・これが根本かな。考えさせられるねぇ。
...もっと詳しく |
ドイツ全土から、2007年1月1日よりゲージ飼いのニワトリ達がすっかり消えた。全ては大地の上で飼育されている。ヨーロッパ全体では2012年から実施するという。いい話ですよ、人間であろうがなかろうが、幸せにつながる話は歓迎だ(「ゲージ飼いは法律違反」バックナンバー)参照。
確かに世界中の生き物達の中でゲージ飼いのニワトリたちほど不幸な動物はいない。羽を持っていても飛ぶことはおろか、広げることすらできず、足があっても歩くことができない。お日さまを拝むことも、風をうけることもなく、両脇に隣人の体温を感じ、対面に自分と同じように苦しむ同輩を眺めながら、長い一日を過ごしている。うわぁーぁ、やりきれないねぇ・・・。 彼らを生き地獄から救ったのは消費者運動だという。ドイツ政府に働きかけ、実現した。自分達が手にする食べ物の質を問題にするだけでなく、そのつくり手の状態にまで思いの範囲が及んでいるということか。 他方、日本の消費者運動はどうだろうか。残念ながら自分達が食べる卵の安全・安心を問題にしても、ニワトリ達をゲージから解放しようという声は聞いたことがない。思いはそこまで到達していない。自分(達)に、問題のない食べ物が手に入るなら、それから先のことには...ということか。 話が変わって、日本の米作りの現場。東北農政局が発表したH18年度の生産原価は15,052円/60kg。農家がJAに売り渡す価格は12,000円/60kg前後。作れば作るほど赤字が出てしまう。H19年もH20年も同じだった。こんな原価割れの米作りが数年続いている。農家の平均年齢は67歳。当然のことながら若がえる兆しはまったくない。いまさら転業もできないから・・という年寄り達の思いだけが継続の原動力だ。(これもバックナンバー参照) 我が村も都会の生協と米作りの提携を行っている。農薬や化学肥料を減らした米作りで、ここでの取引価格は市場の実勢価格プラス1,000円加算だ。30年前は22,000円/60kgに1,000円加算だったが、今日では12,000円に1,000円加算。加算したとて生産原価に遠くおよばない。 ニワトリ同様、思いは生産現場まで到達していない。 少なくとも生産原価を割るような価格ではなく・・と思うが、依然として変わってはいない。すでに農家にとって、農協を通じた生協との提携は「希望」ではなくなっている。そこに出荷しても暮らしていけないのだ。「オールタナテイブ」はその外にある。 生協に代表される日本の消費者運動。合併につぐ合併で、運動体というよりも事業体としての性格が強くなり、動きがとれなくなっているようにみえる。 今は時代の転換期。もし、食の安全、環境、持続性、循環・・・の時代的要請に応えたいという気概があるのならーといえば偉そうだけどータマゴやお米に限らず、生産現場を知り、そことの関係をもう一度問い直すことから始めなければならない・・・。どうだべな。 だけどなニワトリたちよ。 かの国のように消費者運動にだけ頼っていてはいかんぞ! 自分でなんとかする道をみつけなければな。 自力解放の道を・・よ。 何ができるかって? 自分で考えるんだよ! 俺達だってその道を歩もうとしているんだからさ。 なんとかなるさ。 なんとかするんだ! (写真は我が家の前に広がる雪原・・東を眺める) ...もっと詳しく |
ある団体の求めに応じて話したものです。長い文章ですし、今までも同じような発言を繰り返していますから、「もう分かったよ」という方も多いかと思います。いまさらという方は飛ばして下さい。
――今年4月、東京都内をトラクターでデモ行進された。その意図は…。 菅野 日本型農業は再生不可能なほどに解体され、傷ついている。このままでは日本から農民がいなくなる。村がなくなる。農民の作るコメを始めとする作物が消えて行く。それもこの国の主人公である国民の知らぬうちに。この機を逃してしまったのでは、もう再生も不可能だ。急いで国民に真意を問わなければならない。そこで「令和の百姓一揆」を敢行した。 振り返れば、戦後の農地解放で475万戸の自作農が誕生し、それ以後、地主に変わり、彼らが中心となって日本の食料生産を担い、文化を守り育て、農村を維持してきた。美しい農村的風景もその産物だ。しかし、1971年の減反政策を皮切りに、政府は一貫して離農を促進し、日本農業の主軸であった自作農を切り捨て、規模拡大を進め、農業の再生産構造を破壊してきた。最近ではIT技術を駆使して更に農民を追い詰め、「効率化」を図ろうとして、いわば「工業的農業」を進めてきている。しかし、大規模化と工業的農業が可能なのは、耕地の3割程度だ。7割の耕地は中山間地にあり、特にその内の5割は山沿いに広がっている。それらを丁寧に耕してきたのは自作農たちだ。その自作農の離農が止まらない。まさに日本の農業が崩壊しようとしている。減反政策と、長年続いた米や乳価のあまりの安さがその背景にある。このままでは日本から農民が消えてしまう。警鐘を乱打して、国民に問わなければならない。「これが日本の国づくりか?」「これが国民の求めるところか?」と。それが、私たちが行った「令和の百姓一揆」だ。 ――今の大規模経営の農業政策は、日本では非効率的で環境にも悪く、持続性も乏しいという事だが、何か解決策はあるのか…。 菅野 農水省は水田農業従事者の時給を直近で97円と公表している。その前年は10円が二年続き、その前年が207円だった。当然のことながら、暮らしていけることなど不可能で、そのため離農する農家が増え続けてきた。経営の厳しさは大規模経営とて変わらない。大きい分、生産資材や機械代金も嵩んでいくからだ。この流れを止めるためには、やはり所得補償しかない。少なくとも、国が生産費を補償し、再生産が可能になる環境を作る事が日本の農業再建の第一歩だ。 EUやアメリカではそれができている。穀物の市場価格が如何に変動しようとも農家の収入は補償され、その差額を国が補填する。それによって次年度も作付けが出来、後継者も確保できる状態を政策的に作っているのだ。 これまで時給10円と言われながらも農家が稲作を続けて来たのは、農家にとっての稲作が単なるビジネスではなく、祖先が汗水流して守り続けてきた農地を引き継ぎ、後世に繋いでいくという、中継のランナーとしての使命感があったからだ。だが、もはやそれも限界だ。使命感だけではお米を作り続けることができない。それが、離農が相次ぐ今の稲作の現状だ。 私には自公政権が一体どのような国づくりをしようとしているのかが分からない。だが、稲作農業を切り捨てる政策は根本的に間違っている。国民をいのちの危機に追いこんでいるからだ。早急にしなければならない政策は、生産農家の所得補償である。 「何か解決策はあるのか」の問いへの答えは、使命感をもって田んぼの隅々まで耕してきた戦後自作農を守ること。時の政権の農業潰しから日本農業を守ってきた。そこからの始めて、小農からプランター農園に至るまで「国民皆農」を促進することだろうと思う。 ――在宅ワークで地方移住を求める人が増えている中で、農業に興味を持つ若者も多くなっている。農業従事者をもっと増やしていくために、補助金以外に考えられる対策は…。 菅野 農業に興味を持つ若者たちの存在はうれしいですね。彼らが求めているものはたぶん、自然の中での子育てや、農に根差した自給的くらし。できれば自分(達)の食べ物は、自分(達)で作りたいという事だろうか。多くの場合、彼らは農業で食いたいのではなく、まずは農業と共に生きたいのだと思う。よって彼らがやりたい農業は、農薬、化学肥料に依存した工業的農業ではあるまい。自然と共生する、自然の摂理を織り込んだ農的暮らしなのだ。 そんな彼らの為に我々ができることはなんだろう?まず、彼らに必要な家屋や農地を手にするための手助けや、作物づくりの為の技術的な支援などであろうが、ケミカル漬けになっている多くの農民の技術や感性では、彼らの求める助言はできまい。せいぜい要らぬお節介をしないようにすることかな。ただ農地の取得や家屋を一緒に探すことは近隣の農家の手助けがあった方がいい。 ――農業協同組合(農協)の在り方について思う事は…。 菅野 インターネットの普及で生産者から消費者まで直接販売が可能になったのだからと、農協の存在に疑問を呈する声もあるようだが、たぶんそれは農業の現場を知らない人の声だ。稲作に関して言えば、農民が刈り取ったコメは農協によって一括購入され、集められた大量の米は農協の管理のもと低温倉庫で貯蔵され、適切な時期に中間卸に渡されていくという仕組みがある事で、農家は自分の作業舎に倉庫や品質を保つための大型低温倉庫を持つ必要がない。とくに、自分で販売する力を持たない小規模農家にとって、この仕組みは欠かせないものだ。 ――米価格の値上がりと農協の関係をどのように見ているのか…。 菅野 米価が下がらない原因として農協の存在を指摘する声もあるようだが、関係がないと思える。農協のトップには農水省の関係職員もいる。農水省の意向と違う方針はとりにくい。それがまた、生産者の農協への不満と苛立ちの原因にもなっているのだが。 ――地域と一緒に農業を立て直すことは「自給自足」につながり、それは結果的に日本の国防にもなる…。 菅野 これまで、時代の流れは「より多く開発し、より早く発展する事」を求めてきたが、これからのキーワードは「生き残る事」、つまり「生存」だ。米国がトランプ大統領のもと自国優先の政策に舵を切ってきたが、日本も自国民約1億人の食料を、例え天変地異が起こっても困らない様な農業政策に舵を切る事だろう。38%の自給率のままならば食料を持っている国のいう事を、ただひたすらに聞かなければならなくなってしまうに違いない。国の尊厳に関わることだ。またそれ以上に子どもたちのいのちの未来に関わることだ。そのためには、農民の離農の流れを一刻も早く食い止め、農地に農民がいて充分に生活していける当たり前の農村社会を取り戻さなくてはならない。 冒頭で東京でのデモ行進では、六本木や原宿などの若い人たちから嬉しい反応や声援をもらったといったが、よしんばこれから若者たちが農業に興味を持ってくれたところで、そこで暮らしていける保障が無ければ新規参入は難しい。 「隗より始めよ」という格言がある。大きなことを成すには、まず手近なことからという意味だと思うが、今、農業を担っている人たちが幸せでなければ、そこに人は集まらない。農の現場からプロ(農民)が逃げ出すようではそれも難しかろう。まず「農家に所得補償を」である。時給97円では、日本の未来に絶望しかない。 我々は政府、関係機関に向かって要請するだけではない。この日本農業の崩壊局面という日本国民の大きないのちの危機にあたって、思想信条、政党政派の違いを超え、大きな視点に立って大きな連携を創り出し、協力していかなければならない。その為の「令和の百姓一揆」だったのだ。我々も全力で頑張って行く。 |
しばらくブログを休みにしていました。
雨続きの、不快な気候が続いていますが、お元気ですか? 休みの間いろんなことがあったんですよ。先日もこんなことが・・。ひとつずつ紹介していきましょう。以下・・・。 朝起きて、何気なく道路わきに止めてあったトラックを見たら、荷台に鳥かごらしきものがあり、中で何かが動いている。なんだろうと思って近づいてみると、生まれて40日ぐらいの二羽のニワトリが入れられていた。息子に聞いてみても知らないという。では・・どうしてここに・・・?・・捨て子か!・・・捨て鳥だ。 そういえば、その10日ほど前、3〜40代の女性から「子どもが何かの景品にもらってきたヒヨコが大きくなって困っている。引き取ってもらえないか。」という電話があった。 その時は丁重にお断りしたのだが、彼女なのだろうか。名前も住所も聞かなかった。ま、詮索してもしょうがないが・・。 子どもではない、捨てていったのは親だろう。それにしても、自分の家庭の厄介モノを、縁もゆかりもない他人の家に捨ててくる・・・、そのことで自分の悩みを、他の人の悩みにしてしまう・・・なんとも切ない話で、子どもに人の道を教える以前の問題だ。 お店の景品かお祭りで売られているものは、ほとんどがオンドリだ。この幼鳥もオンドリに間違いはあるまい。確かに我が家にはたくさんのニワトリがいるし、一群に一羽、全部で12羽のオンドリがいるが、だからといって・・・。今でさえ、朝4時前から一斉に始まる時の声はご近所の迷惑になっている。これ以上は飼えない。 ちなみに、我が家の90歳になる年寄りに聞いてみた。 「川の土手か、他の人の家に捨ててくるんだぁ。だってしょうがないもの。誰かに拾ってもらえ、大切に育ててもらえって手を合わせてなぁ。少しのエサも付けてやれ。」 なんだぁ、違うのはエサのところだけか。我が親ながら、いい歳のとり方はしてないな。 結局は、我が家で飼うことになるのだろう。なんともやり切れない話だよ。 (写真は入っていた鳥かごと二羽) ...もっと詳しく |
|
8月2日は、「食、農、エネルギー、住、教育」の地域自給を進める社団法人・置賜自給圏推進機構の結成総会です。おいでになりませんか?
置賜の方は是非参加していただけたらありがたい。 会員として一緒にやりませんか?賛同会員もあります。 遠くの方もご参加ください。会員、賛同会員としても歓迎です。 一緒に、参加、循環、自立、自発・・の扉を開けませんか! そこから日本、アジア、世界に合流していきましょう。 http://okitama-jikyuken.jimdo.com/ |
お元気でしょうか?
いろんなことがありましたが、私どもも元気で農業を営んでいます。 さて、ブログにおいでの皆さんに、我が農園の本業である自然養鶏の玉子のことでご相談があります。 いま、玉子が少し多めに産んでいまして、食べていただける方をさがしています。 若鶏の玉子です。 夏はいつも、鶏たちが産まなくなる時期ですがその時期に合わせてヒナを導入した結果、今度は多く産みすぎて困っています。 若鶏の玉子ですので、少し小さめですがプリンとした形状です。 スーパーの玉子で言えばS,M,LのSクラスでしょうか。 その玉子を1パック300円でお分けしています。 通常の大きさの我が家の玉子は580円/1パックしていますので、小型の分だけすこしお安くなっています。 いつまでもあまり続けるわけではなく、秋から冬にかけて 少しづつ産卵量が減っていきますが、そうですね、あと一ヶ月ぐらいは この状態が続き、今度は足りなくなっていきます。 工場のラインと違いますので、この調整はすぐにはできません。 ヒナの増減から始まりますので最低でも半年はかかります。 そこが生き物たちと一緒にやっている仕事の難しいところですね。 メールでご返事いただければお送りいたします。 アドレスは以下のとおりです。 narube-tane@silk.ocn.ne.jp ご住所、〒番号、電話番号、数量、お届け品ならば先様とお届け主の 両方のご住所が必要です。 お問い合わせは090-4043-1315までお電話ください。 4パック(10個入り)がお送りする際の最小単位です。 (箱の容量の関係です。) 送料は関東ならば630円かかります。 4パックならば 300円×4+630円=1830円となります。 生でおいしく食べられる賞味期限はお届けしてから20日間としています。 クールでお送りいたします。 届きましたら冷蔵庫に入れて保管してください。 お支払いは振込み用紙を同封いたします。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 久しぶりに本業の話でした。 自分のこととなると少し緊張しますね。 |
copyright/kakinotane
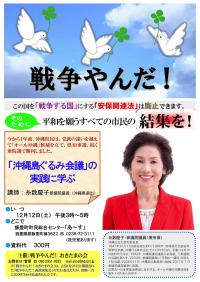











放し飼いの自然養鶏が800羽、水田が2ヘクタール、野菜畑が少々の「有畜複合経営」だ。かつてNHKの番組にあった「大草原の小さな家」のように暮らしていければいいかなと思っている。ちょっと格好のつけすぎかな。
今からおよそ30年ほど前。26歳の春。農家の後継者として農業を継いだときは、農協が指導するからとか、改良普及所がこういうからではなく、農業するものの生き方、哲学が反映する農業を志したいと思っていた。
金太郎飴のようなどこにでもある類型化された農業ではない農業、それを表して「芳秀飴農業」といっていた。
その中味は「二つの大切、四つの基準」と言っていたのだが、大切なことは「楽しく過ごすこと」と「豊かに暮らすこと」の二つだ。それを実現するための四つの基準は「食の安全と環境を大切にする」「暮らしの自給を追求する」「きれいな景観をつくる」「家族みんなが楽しく農業に関れるよう努める」だった。
気負っていたねぇ、あの頃のオレ。
子ども達には「今日は田植えなので学校を休みます。」とか「稲刈りなので・・」、「雪下ろしのために・・」などと理由をくっつけながら、よく小学校を休ませていた。
「楽しくなければ人生じゃない、おもしろくなければ百姓じゃない。」今はこれかな。
「おもしろきことのなき世をおもしろく」という高杉晋作の辞世の句のパクリだけどね。
...もっと詳しく