ぼくのニワトリは空を飛ぶー菅野芳秀のブログ
最近、主要な農作業は息子にまかせ、実務労働に特化していますが、飯は美味いし、酒も美味いので肉体は動かさないくせに今までと同じような食生活を続けていましたから太る一方でした。ここに来てようやくそのバカさ加減に気付き、食事を減らしています。6kgほど減って、目標まではあと7kg。え、そんなに!と思う必要はありません。少し古い例えですが、小錦から数キロg取ったってあまり見かけは変わらないのと同じように、私も6kgぐらい減ったところで外見上ほとんど変わっていません。
かの大谷選手は193cmで102kgだそうですが、私は今、191cmで102kg。ほとんど大谷君と一緒。それを言うと周りに軽い笑いが起こり、私はすこし「キズ」つきます。 コロナがヒト治まりしたらお気軽においでください。大リーグ迄行かずとも、山形においでになれば、大谷君に会えたような気に・・ならないかな。 |
|
10日の晩、「置賜自給圏推進機構」の呼びかけで、地域でとれた大豆を地域で加工し、地域で食べることのできる、そんなまちづくりを目指しての「大豆プロジェクトモデル事業」の初会合が行われ、事業のスタートを切った。
豆腐、納豆、みそ、醤油など大豆加工食品はたくさんあるけれど、圏内大豆と輸入大豆との価格差が大きく、地豆の良さを充分に理解しつつも、一部の例外を除き、なかなか取り組めない現実があった。 そこで今回、関係する方々が集まり、生産から消費までのモデル事業をともにすることで、なんとか地産地消の糸口を見いだせないかと話し合った。 会合にはJAなどの生産者(団体)、トーフ、納豆、みそなどの加工業、スーパー、生協などの流通・販売業、消費者団体、それに市や町、県の行政関係者、商工会議所、置賜自給圏推進機構の関係者など25名ほどの人たちが集まり、事業の主旨、目的、課題などを話し合い、モデル事業のスタートを確認しあった。 地域の主人公はそこに住む住民だ。いま、地域をどう形作っていくのか。そんなことを考えながらの一年が始まる。 |
|
10月31日から11月3日まで、長井市民4人で福岡県大木町、みやま市に行ってきました。
大木町で開かれたシンポジュームで、長井での地域づくりの経験をお話しするように求められたからですが、両市町とも資源循環型社会づくりでは日本のトップランナー。私たちの方が学ぶことの多い集会でした。 ...もっと詳しく |
田植えの最中だ。田んぼの周りにはオオイヌノフグリ、忘れな草、我が家の周辺にはつつじ、すもも、かりんなどの様々な草木が花を咲かせていて、疲れた身体を慰めてくれる。
久しぶりに花に誘われて、さくらんぼの木の下でポーズをとってみた。のどかなひととき。でもひとたび苗代に目をやれば、僕ののびやかな心がかき乱される。 原因はスズメ。育ててきた稲の苗を突っついては、次々とダメにしてしまうのだ。その被害が少しだけならばかわいいスズメ達のこと、大目にも見るのだが、全体の一割にも及ぶとなると限度を超える。 「モミをねらっているのだよ。芽が伸びて葉が茂ってしまえば来なくなるさ。」 被害の出始めの頃、近所の人達はそう言って慰めてくれた。ぼくもいままでの経験からいってその見方に間違いあるまいと思っていたのだが、甘かった。葉が茂り、苗となって田んぼに植えることができるようになっても被害が続いた。 大きな声を出したり、ほうきを振っておどかしたり・・・。そのときは追い払うことができてもすぐにまたやってくる。きらきら光る「防鳥テープ」を張り巡らしてみた。苗代全体に釣り糸を張ればいいと聞いて、それもやってみた。でも全くといっていいほど効果はなかった。大切な苗代はさながらスズメ達の日常的な食卓か、いい遊び場となってしまった。にぎわいながら木々と苗代の間を往復している。 そんなスズメ達をこの冬のあいだ中、ずーっと僕が援助していたのだから情けない。 僕は雪におおわれた冬の間、さぞひもじかろうと、鶏舎に入ってニワトリ達のエサをついばんでいるスズメたちを、追い払わずに見逃してきた。彼らがえさを作る作業小屋にも入ってきて原料を食べている時だって、僕はそれを追い出したりはしなかった。そのことでスズメたちはずいぶんと助けられたに違いない。元気に冬を越せたはずだ。なのにというべきか、その結果というべきか、いま彼らは活発に僕を困らせている。そう思うと複雑な気分だ。 「いいか、よく聞けよ。『舌きりスズメ』の話しを知っているか。お前達の祖先は決して恩をアダで返したりはしなかったぞ。立派な祖先を持ちながら、どうしてお前達は僕を困らすのだ。」 しかし、よく考えてみれば、スズメ達は、自分達が生きるために目の前の食べ物に手を出しているだけだ。ただそれだけのことだ。それを「恩」だ「アダ」だと言わずに、僕は僕で生物の一員として、自分達の食べ物を守るために、スズメ達を追い散らかすだけでなく、場合によってはやっつけてしまえばよかったのだ。切羽詰っていたら必ずそうしただろう。そうしなかったのは、決して優しさからという類のものではなく、「食」に対する切迫感という点で、それほど深刻ではなかったからだ。 「食」の前ではスズメ達より僕の方が甘かった。 冬の鶏舎でも苗代でも、スズメ達の気迫勝ち。 そういうことだよ、よしひでくん。 |
「よしひでぇ−、早く来てくれぇ」
この間のことだ。お昼の少し前、大声で呼ぶ親父の声が聞こえた。あぁ、またか。そう思いながら僕は急いで声のする方に走っていった。 やっぱりそうだった。ニワトリ達が畑一面に散らばって野菜を食べている。ここは両親が作っている野菜畑。ばあさんも加わり一緒に棒をもってニワトリ達を出口に追い込もうとするが、すばしっこく、なかなか思い通りの方向には行ってくれない。逃げるニワトリ、追う僕たち。80才を越える両親はよたよただ。後でこってりと怒られることになるなぁ。そう覚悟しながらニワトリたちを追い続ける。 僕は1,000羽のニワトリをなるべく自然に近いかたちで飼いたいとおもっている。健康な玉子を得るためだ。ニワトリたちは壁のない開放型鶏舎の中で暮らしているが、3〜4日に一度は外に出る。広い草地、お日さまが照り、虫達がいて・・・。これで充分だと思うのだが、まだ足りないらしい。わずかなすき間を見つけては畑の方に侵入してくる。両親には悪いがこれも仕方がないことだと思っている。それだけ元気なニワトリがいるということだから。 僕がこのようにニワトリ達を飼っているのは、健康でストレスの少ない毎日をおくりたいという彼等の願いと、おいしい玉子を食べたいという僕たちの願いとはかなりの点で一致すると思っているからだ。だから僕はニワトリ達にとってこのほうがいいのではないかと思えることをできるだけやるようにしてきた。鶏舎の中では一羽あたりの空間を広くとり、エサはなるべく多くの種類を与え、水は朝日連峰の地下水だ。外にでて一日中あそぶこともできる。 話しは変わるが、鳥インフルエンザの事件は、テレビを通してケージに飼われたニワトリたちの過酷な日常生活を写し出した。薄暗い鶏舎の中、小さなカゴにぎっしりと詰め込まれているトリ達。ストレスのなかで、いのちのない卵を産み続ける毎日。 このニワトリ達ほど不幸な動物は他には思い当たらない。動物園の象だって動き回ることはできるのだから。僕がその中のニワトリだったら、よしんばインフルエンザにかかることなく生きながらえたとしても、そのことを素直にはよろこべないだろう。 ニワトリ達を閉じ込めているのは、その方が手間がかからず効率的に卵をうむからだ。ここにはニワトリを不幸にしても人間の利益になればという構図がある。でも僕にはどうしてもニワトリを不幸にすれば、まわり回って人間もまた不幸になっていくように思える。 だから僕にはカゴはいらない。 |
自然養鶏に取り組むようになってからほぼ20年になる。その間、へぇ〜と思う「小さな発見」がいくつかあった。「山の神様」との出会いもそんな発見の一つだ。ちょっとしたことがきっかけだった。僕が親愛を込めて「山の神様」と呼んでいるのは地元の微生物のことだ。 ある日、鶏舎から外に出たニワトリ達をぼんやりと眺めていたら、多くのニワトリ達が土を突っつき泥水をすすっていることに気がついた。鶏舎の中にはエサがあるし、きれいな地下水が間断なく注いでいるのに何を求めての土や泥水か?しばらく思いめぐらした後、僕の得た結論は、単に水分や土中のミネラルを取り込もうとしているだけでなく、それらの中に含まれている「地元の微生物」を体内に取り入れ、身体の内と外との調和をはかろうとしているのではないかということだった。 それぞれの地域には、その地その地の環境に見合った「地元の微生物」がいる。わずか1gの土の中に数億とも数十億ともといわれるおびただしい数の微生物たち。そのもの達は土だけではなく、大気中にも、植物の上にも、水の中にも、僕達の皮膚にも、体内にも・・・と、どこにでもいてくれて、生きている者たちの生命活動を支えている。 人間の赤ちゃんは生まれたときは無菌状態だが、三日の後には必要な微生物が体内にそろい、以来いのちが尽きる日まで連れ添ってくれるという話しを聞いたことがある。 人間だけでなく地域の動物達も、草や水、あるいは土を通してその微生物を体内に取り入れ、身体の内と外(自然)との「調和」をはかっているのだろう。 むかしから「三里四方の食べ物を食べよ」というのは、それぞれの地域の「地元の微生物」に依存して暮らすこと、あるいは「微生物による調和」の大切さを教えたものだろうと思っている。 僕はエサを醗酵させて与えていた。醗酵させたほうが無駄なく吸収できるためだ。当時、醗酵菌は県外の(富山県の)ものにたよっていた。 しかし、よく考えたら、ニワトリの周辺には朝日連峰の微生物、体内には富山県の微生物。このような組み合わせは自然の動物にはありえないことだ。ニワトリ達はこの不調和を是正しようとして、土や泥水を食べようとしたのかもしれない。そう考えた。 自然との調和は健康の源であり、いい玉子は健康なニワトリから産み出される。この地域の微生物でエサを醗酵することはできないだろうか?それができたらニワトリ達の生態と自然とのハーモニーがしっかりと築かれ、養鶏の枠の中とはいえ、さながら野生のタヌキやヤマドリたちと同じ世界が実現できるはずだ。地元の微生物をいただきに行こう。 パワフルなのはやはり森の中。山に分け入り、ラーメンどんぶり一杯分ぐらいの腐葉土をいただいてきた。それを大きなバケツでそれぞれ6杯ぐらいの米ぬかとノコクズとでまぜ合わせ、小山状態にして様子をみた。腐るなら嫌な臭いを出すだろう。醗酵ならかぐわしい香りを放つはずだ。どきどきして見守った。3日後の朝、シャッターを開けたらエサ場の中いちめんにいい香りが広がっていた。小山に手を入れてみる。熱い。60度はあるだろうか。なんと力強い醗酵だ。 それは同時に、太古の昔から生命の循環をつかさどって来た地元の微生物との感動的な出会いだった。僕は思わず、「これは山の神様だ。」とさけんでいた。あなたはこのときの僕の喜びを想像できるだろうか? さっそくそれをエサ全体に混ぜた。エサは同じような香りを放ちながら醗酵していった。これでようやく野生と同じ「調和」が実現できる。僕のニワトリは地鶏になれる。そう確信できた。 その日から今日まで、ニワトリ達は山の神様のお世話になっている。おいしい玉子を産んでいることはいうまでもない。 |
吹雪の中、鶏舎に入っていくと、スズメとニワトリがエサを分け合っていた。いいぞぉ、生き物同士だ。困っているときはこれでなければいけないな、ウン。見ている僕の中にも、ほのぼのとした思いがうまれてくる。
ひよこ屋さんがやってきたのは去年の春ごろだったかな。彼は外で遊んでいたニワトリ達をみながら「ずいぶんとのどかな風景だねぇ。ところで伝染病対策はどうしている?」と聞いてきた。ゲージ養鶏のようにかごに入れ、宙に浮かしているのと違って、同じ地面をたくさんのニワトリ達が踏む。伝染病が広がりやすいのではないかというわけだ。 「このように遊ばせておくこと自体が対策かな。あとはきれいな水と新鮮な空気、それにいい食べ物だね。自然養鶏を始めてから20年になるけど、伝染病はただの一度も経験していないよ。」と答えたが、彼はとても考えられないことだとしきりに首をひねっていた。でも事実なのだから仕方がない。 そのひよこ屋さんがスズメとニワトリが一緒にいる目の前の光景を見れば、きっとまた「伝染病の・・・」といいだすだろう。昨年の「鳥インフルエンザ」以来、指導機関も防鳥ネットだ、窓なし鶏舎だと野鳥に対する警戒を呼びかけ、補助金を出してニワトリ達をいっそう自然から切り離し、隔離する方向へ誘導しようとしている。 「だけどね、ひよこ屋さん・・・」とやっぱりいいたいよな。人工的に隔離されたニワトリ達がいともたやすく死んでいくのは病気への抵抗力が弱いからだと思うよ。これを更に隔離する方向に進めたのではもっとひ弱なニワトリができてしまうだけだ。悪循環だし、そもそもそんな卵はおいしくないよ。 求められていることは自然の遮断ではなく、できるだけ自然のなかで、自然とともに飼い、ニワトリの本来もっている生命力、抵抗力を高めていくことで病気を克服することさ。そんなニワトリが産んだ玉子だからこそ、おいしいし、身体にもいい。スズメだって自然の一部だ。一緒にいたっていいんだよ。 こんど彼が来たら、こんなことを言ってやろうと思っていたら、「北朝鮮に鳥インフルエンザ発生。10万羽を処分」のニュース。うわっ、またか。 だけどね。うふふ、負けないよ。この機会をつかまえてね、日本国中のニワトリが、自然ともっと近付いて暮らせるように変えてやろうと思っているんだからさ。 そうだよね、同志諸君。 |
東京からは桜が散ったという便りが届いているのに、こちらはまだ桜どころか梅の花も咲いてない。でもようやく鶏舎の周辺から雪が消えた。 ニワトリ達は久方ぶりに鶏舎の外に出た。あいにくの小雨模様。それでもほとんどが外で遊ぶ。土の上はほぼ4ヶ月ぶりだろうか。一気に駆け出すもの、飛ぶもの、土をついばむものなど様々だけど、みんながうれしそう。雪に閉じ込められて、ずーっと鶏舎のなかだったのだから無理もない。退屈でもあったろう。さぁ春だ。思いっきり遊べ!なんだか見ている僕の方もウキウキしてくる。 だけど一方で、ゲージの中で飼われている大部分のニワトリ達にとっては、あいかわらず冬も春もない切ない毎日が続いている。さぞや「むなしい人生だ」と力を落としているに違いない。苦しいだろうなぁ、つらいだろうなぁと思っていたら、とても興味深いニュースが飛び込んできた。 ドイツでは2007年1月1日をもって、採卵鶏をゲージで飼うことが法律で禁止されるという。これによってニワトリ達は自然な方法でエサや水をとり、砂浴びができるようになるということだ。EU全体でも2012年から実施するという。これはすごい。とてもいいニュースだ。 ヨーロッパでは以前から「動物福祉」という考え方を育ててきていて、ニワトリだけでなく、牛や豚など家畜全般に対して、なるべく苦痛を与えない環境で飼おうとしてきた。 やっぱり、かの地の人々にはかなわないなぁ。家畜に思いやる気持ちが国を動かすほどの世論になっているということかぁ。 他方、日本ではどうかといえば、ニワトリ達のまわりに、そんな風は少しも吹いていない。比較的敏感な生協などでさえ、たまごの安全性にはこだわっていても、ニワトリ達をゲージから解放しようという取り組みまでは聞いたことがない。 どうしてだろうか。何故、日本ではこのような世論がそよとも起こらないのだろうか?日本人は冷たい民族なのかい?いやいや、僕は決してそうは思わない。 原因は、ただやたらに忙しいからだと思う。たとえば都会で働く多くのサラリーマンにとっては、隣人にさえ、ある場合は自分の家族に対してだって思いを寄せる余裕がないほどの毎日だと聞く。とても家畜にまでは及ばないということだろうか。 家畜たちをゲージ飼いの世界に追い込んでいるものは「経済効率」というモノサシだが、そこから、彼等を自由にしようとしたら、まず我々自身が自由にならなければならないということだろうか。 うわっ、根が深いぞ、これは。困った。どうしましょうか? |
山菜がおいしい季節だ。 鶏舎の周辺で仕事をしていたら、幼馴染の正雄さんがやってきた。山に行って山菜をとってきたから食べに来いという。彼は山菜とりの名人だ。雪どけを待ちかねたように山に分け入り、山菜をさがす。僕もときどき彼の家に押しかけてはそのおすそ分けにあずかってきたのだが、今回はわざわざ呼びに来てくれた。これは期待できるぞ。さっそく仕事をたたんで彼の家に向かった。 やっぱりね。テーブルいっぱいにワラビ、ミズなどの定番に、アイコウ、シオデ、シドケ、それにまだ見たこともない山菜の数々が並んでいる。 「これは何だか知っているか?」「今度はこっちを食べてみろよ。」 すすめられるままに口に運ぶ。いいねぇこの香り、この微妙な味わい。野菜とは違う独特の風味が口の中いっぱいに広がっていく。まだ日が高いけど、山菜と焼酎を交互に口に運んでいるうちに、酔いがまわってきた。なんというか・・・今日はいい日だよ。 ところで・・と、正雄さんが話しだした。 「この山菜が食べられるということが分かるまで、つまり他の多くのものは食べられないということが分かるまで、いったいどのぐらいの人が犠牲になったんだろうか?」 すごい話になってきた。想像がつかないけれど、ある草を食べてお腹が痛くなったり、ゲリで苦しんだりという体験は嫌になるぐらい繰り返してきたはずだ。亡くなった人もいただろう。もちろん、二度と同じ苦しみをしないように、親から子に、あるいは周囲の人たちに一生懸命伝えようともしてきたに違いない。でも、それらの情報が伝わる領域には当然かぎりがあり、幾度も同じような悲惨な体験をあっちの村で、こっちの集落でと繰り返しながら、少しずつ選びとる知識を積み重ねてきたということか。 それは食べ方にも言えて、たとえばワラビをそのまま食おうとしても、とても苦くて食えたものじゃないけれど、やがて今に伝わっているように、灰をいれて湯がけばおいしくなるという食べ方を発見するに至る。苦いからといって捨てなかった。あきらめなかった。あきらめずに何とか食べられる方法を見つけようとしてきた。 全ての植物は、人間が食べられるものと食べられないものとに分けることができるが、食べられるものとして分類されてきた植物の一つひとつのなかに、飢えと背中あわせにものを食べてきた人びとの、命がけの体験が宿っているということなのだろう。 なぁ、正雄さんよ。なんだかこの目の前の山菜がいとおしくなってきたよ。変かもしれないけど・・食べながら・・涙が・・。 もうすっかり酔っぱらっちまった・・・。 |
また鳥インフルエンザが発生した。茨城県水海道市の養鶏業者で、2万5千羽を処分しなければならないという。さぞ辛いだろう。何よりも処分されていくニワトリ達がかわいそうだ。 「インフルエンザのニワトリにBSEにかかった牛、それに去年はコイヘルペスの鯉もいた。それらを人間はちゃんと食べて上げるべきだとおもうよ。『フライド<インフルエンザ>チキン』や『BSEどんぶり』、あるいは『ヘルペス鯉のうま煮』とかにしてさ。」という電話をよこしたのは東京に住む友人だ。彼女は怒っていた。 「生産効率だか何だかしらないよ。でもね、動物や魚達を狭いところにゴチャゴチャと押し込み、いろんなものを食わせ、本来もてたはずの病気への抵抗力を奪っておいて、その上食いもしないで殺しちゃうなら、生まれてきた意味がないよ。わたしがニワトリや牛や鯉なら化けてでるね、きっと。食べるべきだと思うよ。食べてその罪を自らが引き受けるべきだよ。」 友人の化けた姿を想像して思わず笑ってしまったが、話していることはしごくまともなことだ。 人は食べ物がなければ生きていけない。人間の世の中がこれから先も続いていくことができるとすれば、それは食べ物の生産のあり方に無理がなく、いつまでも続けていくことができるという条件があってのことだ。それがなければ、当然のことながら人の世も続かない。鳥インフルエンザやBSEとして現れていることは、まさに人の世と食べ物生産の持続性にかかわることだ。問題は両者の健康な関係をどう築きなおすのかということ。大いに議論すべきはそこのことなのに、BSEのことでは「吉野屋の牛丼」の話ばっかりだったし、今度のことだって茨城の養鶏場の人たちが不運だったなんて話しで終わりかねない。これでは殺された数万、数十万の魚や動物達は浮かばれないだろう。 茨城の発生をうけて、業界ではまたぞろ鶏舎に野鳥が入らないようにと、外界とニワトリ達をしっかりと遮断するよう呼びかけている。一層自然界から隔離しようというわけだ。 “彼らを工場生産のラインの上に乗せるのを止めよう、ケージの中に入れるのは止めよう。動物にいきいきと過ごせる環境を。それがわれわれの健康な暮らしの前提なのだから・・”とはならない。そうである以上、これから先も同じようなことが繰り返し、繰り返し起こるに違いない。 でもさ、他は知らないけど、少なくとも日本人は大丈夫だね。どんなに悪いことでもきっと忘れることができるから。その証拠に「コイヘルペス」のことなどはすっかり忘れてしまっているものな。現状は何ひとつ改善されておらず、むしろ悪くなってさえいるのに、対策を考えることなく、みんな忘れていく。まぁ、ぼく達のこのすばらしい能力に乾杯だね。 |
copyright/kakinotane


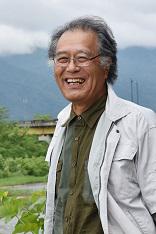










この山間の里からは一万年前の石器が発見されている。以来今日までこの地で数百回の世代交代が行われてきた。
山と水田と村人の暮らしを説明しながら、学生たちに考えてもらっている。
連綿と続いてきた「地域のタスキ渡し」・・・何を願いながらのタスキ渡しだったのか。
そして今、一見豊かに見えるこの村は、急速に衰退に向かっている。同時にそれは日本の食糧生産基地の衰退でもあり、人々は空腹を我慢できないことを考えれば、この衰退は国の自立の危機でもあることを。
首都圏で育った若い学生たちには、大学の教室では話してきたけれど、現場を見ながらの話しは衝撃的だったかもしれない。でも彼らが未来の創り手であることを考えれば、知っておいてほしい現実だ。なおこれからも首都圏で暮らす青年たちならなおさらそう思う。